発達障害をもつお子さんの保育において、こんなお悩みはありませんか?
- 落ち着きがなく、じっとするのが難しい
- 集団の中での参加が苦手
- 周りの子どもたちとトラブルになりやすい
現在、発達障害は広く認知はされているものの、具体的な対応について悩まれている園・保育者の方は多いのではないでしょうか。
かつて私も発達障害のお子さんの保育を経験し、判断に迷ったり、試行錯誤を繰り返したりと、対応の難しさを実感しました。
また、お子さんの対応だけが難しいのではなく、職員間の意見の相違や対応の違いにも悩むことも少なくありません。
とくに発達障害のあるお子さんの対応では、職員間で意見が分かれてしまうという事態も発生しやすいです。
そのため対応が複雑化し、園全体で抱える問題として直面します。もし、そのまま放っておくと、お子さんに大きな影響を与えてしまう可能性があるでしょう。
この記事では、発達障害をもつお子さんのトラブルの背景を理解し、職員間で連携できる対応を紹介します。
また、具体的なトラブル回避策やマニュアル化のコツも詳しく解説しますので、参考までにご覧ください!
発達障害の子どもの保育|なんで「トラブル」が起こりやすいの?

保育現場において、発達障害の特性がどのようにトラブル行動につながるのか、具体的に解説します。
発達障害の特性による行動をチェック
いわゆる「トラブル」が起きやすい行動は、子どもが故意に行っているわけではありません。
実は、発達障害特有の特性によってトラブルにつながりやすい背景があります。まずは、お子さんの特性を理解することが大切です。
以下の特性による行動をご覧ください。
| 特性 | 具体的な行動 |
| 感覚過敏 | ・ざわざわした音が苦手でパニックになる ・特定の感触を過度に嫌がる |
| コミュニケーション | ・自分の気持ちを言葉で伝えるのが難しい ・相手の意図を読み取るのが難しい ・視覚情報をそのまま言葉にする |
| 衝動性・多動性 | ・突然その場から離れることがある ・衝動的に手が出る |
| 見通しが立たない不安 | ・見通しが立たなくて不安で泣き出す ・パニックになる |
「活動や場面の切り替えが難しい」「落ち着きがない」「友だちとのトラブルが多い」といった、保育現場でよく見られる困りごとって、ありますよね。
「困りごと」として処理されやすい発達障害の特性による行動は、理由・背景となる「要因」を取り除くことが必要です。
要因を取り除くことで、お子さんが落ち着いて過ごせる時間が増えていきます。
まずは、お子さんの「困りごと」は、どのような行動・状態なのか?
その行動・状態は、どんな場面・状況で起こりやすいのか?
こまかく把握してみましょう!
また、その際にお子さんの言葉にもじっくり耳を傾けてみてください。言葉の裏にかくれている感情や意図につながることがあります。
発達障害の特性を理解しよう
厚生労働省・国立障害者リハビリステーション・文部科学省などが提供している発達障害に特化したサイト「発達障害ナビポータル」では、発達障害を以下のように明記しています。
| 自閉スペクトラム障害(ASD) | ・他人との社会的関係形成の困難さ ・言葉の発達の遅れ ・興味や関心が狭く特定のものにこだわる 特徴は、3歳までにあらわれやすい。ただ、小学生まで問題が顕在しないことも。中枢神経系に何らかの要因で機能不全があると推定される。 |
| 注意欠如多動性障害(ADHD) | 身のまわりにある「特定のもの」に意識を集中させる脳の働きがある。 注意力にさまざまな問題があり、衝動的で落ち着きのない行動によって、生活上さまざまな困難に直結している状態。 |
| 学習障害(LD) | 学習に必要な基礎的能力「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」「推論する」のうち、1つまたは複数を習得するのが難しい。 また、これらの能力をうまく発揮できず、学習上さまざまな困難に直面している状態。 |
発達障害の特性を知ることで、今後の支援に役立てられます。しかし、同じ発達障害のお子さんがすべて同じ特性・行動としてあらわれるわけではありません。
特性の理解は一般的な知識として備えつつ、まずは目の前にいるお子さんをじっくり観察しましょう。同じ発達障害のお子さんであっても、タイプによって見られる行動は異なります。
また、まだ医師による診断がない場合は、独断で診断名を判断しないように注意しましょう。
トラブルを防ぐ!発達障害児の保育に活用したい「かかわり方の基本」

ここからは、発達障害児の保育に活用したい「かかわり方の基本」を紹介します。
「トラブルを未然に防ぎたい」「子どもが少しでも落ち着いて過ごせるようにしたい」と思っている保育者は必見です。
職員全員が知っておきたい共通の認識なので、ぜひ最後までご覧ください。
環境づくりの重要性
発達障害のあるお子さんにとって、環境はめちゃくちゃ重要です。反対に、環境が合っていないと困りごとを減らすのは難しいと言えるでしょう。
環境を整えることは、お子さんの情緒を安定させます。たとえば、以下の環境づくりを参考にしてみましょう。
| 目的 | 例 | |
| 視覚支援 | 自閉スペクトラム症の特性では、音声コミュニケーションよりも視覚的コミュニケーションが強いため支援が必要 | ・絵カード ・1日のスケジュール表など |
| 落ち着ける場所 | 心理的な安定 | ・静かで落ち着いた部屋 ・隅などのスペース |
| 刺激の調整 | 特定の刺激に対して過剰に求めたり、避けたりする特徴がある。取捨選択の調整が難しいため支援側が行う | ・音、光、匂いなどの配慮 |
発達障害のあるお子さんには、視覚情報が優位という特性があります。そのため、絵カードや1日の流れの表などを使って、適切に視覚支援を行うことが大切です。
また、気持ちが落ち着かないときは、クールダウンできる場所を確保しましょう。さらに音や光などの刺激を支援側が調節することで、安心して過ごせるようになります。
そもそも、環境設定は発達支援には欠かせません。
もし「どこから手をつけたらいいかわからない!」という方は、まずは環境から整えてみることをおすすめします。
補足
発達障害の支援には「TEACCH(ティーチ)プログラム」の特長「構造化」を取り入れた方法が効果的であり、多くの支援施設で取り入れられています。
「TEACCH(ティーチ)プログラム」とは、1972年からアメリカ・ノースカロライナ州で行われている、自閉スペクトラム症の当事者と家族を対象とした生涯支援プログラムです。
この記事でも参考にさせていただきました。
参考元:厚生労働省「自閉症等発達障害児・者を支援する施設・事業所におけるTEACCHプログラム導入方策の調査・研究」
効果的な声かけのポイント
発達障害のあるお子さんには「効果的な声かけ」があります。以下3つのポイントを参考までにご覧ください。
- 「短く・具体的に・肯定的に」伝える
- 「選択肢」を与える
- 「できたこと」を具体的にほめる
「短く・具体的・肯定的」に伝える目的は、話の内容をわかりやすく伝えて理解につなげるためです。反対に「長く・抽象的・否定的」に伝えてしまったら、大人でも聞きたくなくなりますよね。
効果的な声かけは、子どもの発達を理解し信頼関係を築くうえで重要なかかわり方の1つです。
さらに「選択肢」を与えることで、子どもの主体性を引き出します。「自分で決めた」「自分で選んだから、がんばってみよう」という気持ちにつながるでしょう。
とはいえ、やみくもに「がんばったね!」「すごかったよ!」と伝えても、子どもはピンこないものです。「できたこと」を具体的にほめることで、評価ポイントが適切に伝わって自己肯定感が育まれるでしょう。
見通しを立てる支援
「この先に何があるのかわからない…」という状況は、大人も子どもも不安です。とくに発達障害のあるお子さんにとっては、不安な気持ちがそのまま行動にあらわれます。
そのため「見通しを立てる支援」が重要。次のことを意識して取り組むと効果的でしょう。
- 活動の「始まりと終わり」を明確にする
- 事前に「次の活動」を伝えて不安を軽減する
事前に活動の「始まりと終わり」のタイミングを知らせることで、安心して過ごせるようになります。知らせる方法には、時計の針やタイムタイマーなどが効果的です。(個人差あり)
たとえば、好きな遊びの「片付け」のタイミングを事前に伝えておくと、気持ちの切り替えがスムーズになることがあります。また、パニックになる前の手立てとしても有効です。
保育職員の連携がカギ!発達障害への理解をつなぐ「マニュアル化」
とくに発達障害のあるお子さんの保育では、保育職員の連携が不可欠です。職員間の対応に一貫性がない場合は、混乱を招いてトラブルや困った行動が多くなります。
そのため、職員間の統一した対応が必要。全職員でお子さんを理解するために情報を共有し、「マニュアル化」を検討しましょう。
マニュアル化を検討している方は、次の具体的な作成方法を参考にしてみてください!
マニュアルに盛り込みたい項目
まず、マニュアルに盛り込みたい項目について以下をご覧ください。
- 子どもの個別・特性と配慮事項
- トラブル発生時の具体的な対応(声かけ・クールダウンの場所など)
- 情報共有のルール(日誌・連絡帳・共有シートなど)
- 緊急時の対応(安全確保・保護者への連絡など)
子どもの全体像を共有し、配慮すべき内容を記載します。その際にトラブルにつながりやすい場面など記載しておくと安心です。
さらに、実際にトラブルが発生した時の具体的な対応もわかりやすく記載しましょう。また、情報共有にはICTを活用するのもおすすめです。情報を共有する際は、個人情報の取り扱いに注意しましょう。
保育のICT化の関連記事はこちら。
発達障害のお子さんにとって、予想外の出来事はパニックの要因にもなります。緊急時は速やかに細やかな対応がとれるように日頃から体制を整えておきましょう!
補足
前職では、発達障害のお子さんの個別指導計画を作成した経験があります。その際には、保育の5領域「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」の視点をもとに作成しました。
上記の項目に加えて、保育計画の際に活用する5領域を参考に作成することで、保育のねらいと内容に沿った計画を作成できるでしょう。
参考元:保育所保育指・幼稚園要領・文部科学省「第2章 ねらい及び内容」
マニュアル作成のポイント
続いてマニュアル作成では、以下のポイントをご覧ください。
- すべての職員が参加し、意見を出し合う場を設ける
- わかりやすい言葉で具体的に記載する
- 定期的に見直し、改善する仕組みをつくる
発達障害児の保育には、担任1人で抱え込まないで園全体で見守る姿勢が重要です。こうした姿勢は、発達障害の有無にかかわらず、保育の理想の姿でもあります。
とはいえ、専門的な知見・経験がないと適切な対応が難しいでしょう。そのため「保育士向けの研修」などを活用し、実際に学んでいくことが必要です。
発達障害ナビポータルでは「ペアレント・トレーニング等に関する研修」として、支援者向けに収録映像の一部を公開しています。ぜひ、参考までにご覧ください。
補足
今回の記事では「マニュアル化」と解説していますが、保育所指針・幼稚園要領では指導・支援計画として位置づけることを推奨しています。
以下のように明記されていますので、参考までにご覧ください。
⚫︎保育所指針:(指導計画の作成)キ
『障害のある子どもの保育については、一人一人の子どもの発達家庭や障害の状態を把握し、適切な環境下で、障害のある子どもが他の子どもとの生活を通して共に成長できるよう、指導計画の中に位置付けること。(中略)家庭や関係機関と連携した支援のための計画を個別に作成するなど適切な対応を図ること』
⚫︎幼稚園要領:第5「特別な配慮を必要とする幼児への指導」
『(前略)集団の中で生活することを通して全体的な発達を促していくことに配慮し、特別支援学校などの助言又は援助を活用しつつ、個々の幼児の障害の状態などに応じた指導内容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に行うものとする。(中略)長期的な視点で幼児への教育的支援を行うために、個別の教育指導計画を作成し活用することに努めるものとする。』
文部科学省の「第2章 園における障害のある幼児などへの指導」では、合理的配慮、アセスメントなどについて具体的な内容が記載されています。気になる方は、こちらもチェックしてみましょう!
発達障害の子どもの保育は園全体で協力しよう

発達障害のある子どもの保育は、園全体の協力体制が欠かせません。そのために必要な対策として「保護者との連携」「外部機関の活用」があります。
ここからは、この2つの対応について詳しく解説します!
保護者との連携は重要
保護者との連携は、お子さんの成長・発達をサポートするのに重要な役割があります。そのため、日頃からお子さんの情報を共有することが重要です。
園生活において、子どもの長所や気になる行動などを伝えましょう。反対に、家庭の様子も共有することで、対応のヒントにもなります。
ただ、手がかりになる情報を得ようとして、むやみに詮索するのはNGです!
保護者は、さまざまな葛藤や思いを抱いています。園での困りごとを伝える際には、保護者を傷つけない伝え方を意識しましょう。
日々の関係性の積み重ねによって、信頼関係が構築されて連携しやすくなります。
外部機関を活用しよう
発達障害のあるお子さんの保育では、外部機関の活用がおすすめです。保育所等訪問支援、巡回相談などの専門機関としっかり連携をとりましょう!
外部の専門機関には、児童発達支援センター、医療機関などもあります。こうした地域との連携を通じて、園だけでは解決できない課題をサポートしてもらうのが重要です。
発達障害児の保育に関するよくある質問

ここからは、発達障害児の保育についてよくある質問を6つまとめました。気になる内容がありましたら、ぜひチェックしてみてください!
⒈ 診断が出ていない子への対応は?
診断の有無にかかわらず、子どもの「困りごと」に着目しましょう。個別支援は、特性をもとに行います。子どもの行動を観察しながら、安心して過ごせる環境を整えましょう。
園での様子は保護者に伝えつつ、必要な場合は専門機関につなげる働きかけも大切です。長期的な視点をもって、専門機関との連携を検討しましょう。
文部科学省では「特別な配慮を必要とする幼児を含む教育・保育の実践課題に関する実態調査」にて、各保育現場の実態をまとめています。参考までにご覧ください。
⒉ 補助の先生との連携で気をつけることは?
補助に入る保育者と担任が密に連携して一貫性のある対応を意識します。対応のバラつきによる、子どもの混乱を防ぎましょう。
そのためには、日頃から情報をこまめに共有し、発達障害への基本的な理解を深めることが大切です。どのような支援が必要なのか考慮したうえで、具体的な役割を伝えます。
また、保育後は、フィードバックがあると次につながりやすいでしょう。さらに、感謝の気持ちを忘れないで互いに支え合える関係を構築できるのが理想です。
主任や園長などのサポート体制があると心強いでしょう!
⒊ 職員間で意見が違うときは、どうしたらいい?
保育者といっても、経験・知識・子どもの見方はさまざまです。そもそも意見の違いは自然なこと。
とはいえ、意見の違いを放置してしまうと、子どもの混乱やトラブルの長期化につながります。
「子どものため」という共通認識を再確認し、事実にもとづいた客観的な話し合いをすすめましょう。マニュアルやルールを決めたり、見直したりなど、改善する場をつくるのが必要です。
また、最終的な方向性を閉める立場として、園長・主任のリーダーシップを果たすことが求められます。さらには、外部の研修を活用して意見の相違を減らす工夫も取り入れましょう!
⒋ 保護者支援が難しい!どんな対応をすべき?
まずは、発達障害の疑い・診断を伝えられた保護者の心理状態に理解を示すことが重要です。個人差はありますが、少なからず混乱・不安・疲弊などを抱えて受容が難しいケースも少なくありません。
保護者の話に耳をかたむけ、気持ちに寄り添う姿勢が大切です。園での様子を伝える際は、気になる様子だけでなく、子どものよいところや成長を感じた点も具体的に伝えるとよいでしょう。
加えて、園での配慮の目的や効果を丁寧に説明し、保護者の理解も得ながらすすめるのが大切です。保護者1人で抱え込まないように、園が子育てのパートナーとして伴走していく姿勢を示しましょう。
参考元:保育所保育指針(保護者支援に関する内容)
⒌ 発達障害の早期発見が大切な理由は何ですか?
一見気づかれにくい発達障害は、周りの子どもたちと同じように学習面・行動面・対人関係のスキルを求められます。
そのため、ストレス・不安感・自己評価低下などを招き、不登校・ひきこもり・反抗的な態度や行動として適応困難な状態になる可能性があるのです。
こうした二次障害を引き起こす前に、早めに気づいて適切な対応へつなげましょう。
参考元:国立特別支援教育総合研究所「発達障害と情緒障害の関連と教育的支援に関する研究ー二次被害の予防的対応を考えるためにー」
⒍ 療育ってどんなことをするの?保護者にすすめるべき?
療育とは、発達に課題のある子どもを対象に適切な支援を受けられる地域の支援機関です。日常生活の基本的動作・知識・技能を付与し、集団生活への適応訓練などを提供します。
児童発達支援は「児童発達支援センター」「児童発達支援事業」の2種類があります。
参考元:発達障害ナビポータプル「療育」
発達障害児の保育は連携して一歩ずつ前へ

発達障害のある子どものトラブルや困った行動は、適切な理解と統一された対応で減らすことが可能です。職員間で情報を共有し、園全体として支援できる体制をつくりましょう。
そもそも発達障害のお子さんの支援は、発達障害を抱える親子だけの限定的な支援ではありません。実は、周りの子どもたちにもよい影響を与えます。
子どもたち同士が互いの違いに気づき、受容しながら過ごしやすい園生活を送ることができます。こうした経験は、今後の社会生活において必要な力になるでしょう。
読者のみなさんの園では、いかがでしょうか?
さらに具体的なマニュアル作成のヒントや研修について知りたい方は、ぜひ外部の専門機関を活用してみましょう。
まずは小さな一歩から、全職員の力をあわせて取り組んでみませんか。








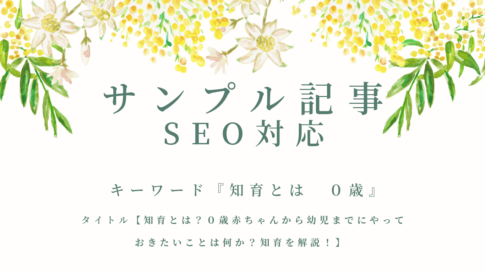



コメントを残す